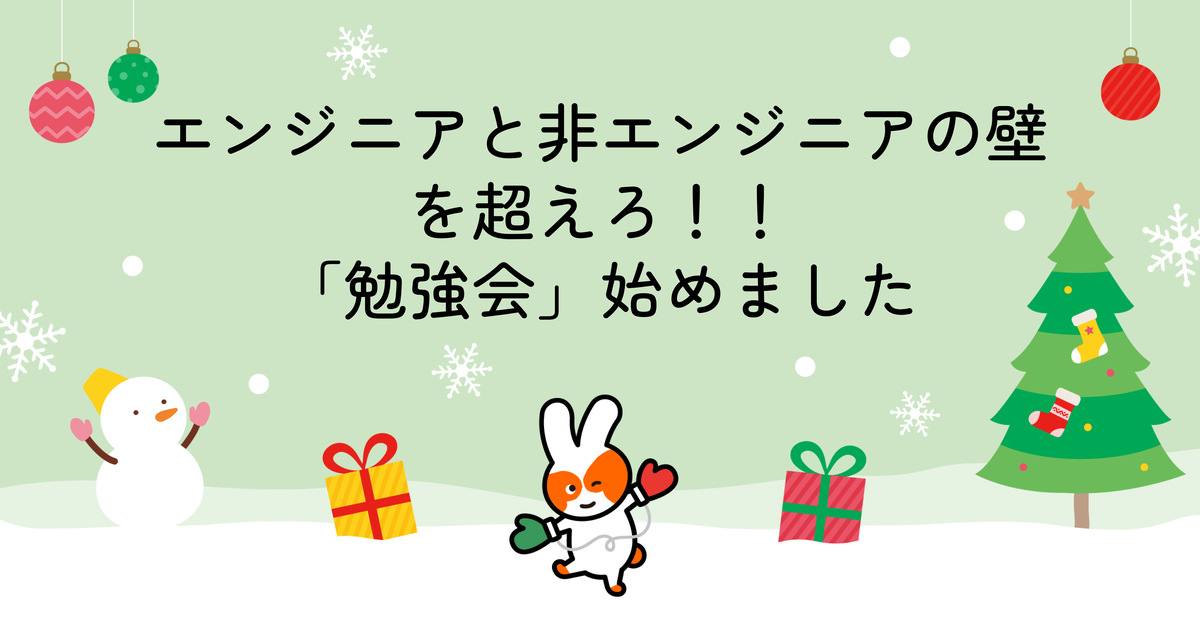 こんにちは!千株式会社ものづくり部CTO室のSAWAです。
こんにちは!千株式会社ものづくり部CTO室のSAWAです。
この記事はSEN Product Blog アドベントカレンダー 2024 の14 日目の記事です。
はじめに(自己紹介)
データ分析基盤を構築するプロジェクトメンバーとして千株式会社にジョインしました。「データに基づいた意思決定と戦略の立案の支援」がミッションです。BIツールを使って、視覚化や課題の提案、解決をしていくことが好きです。※Tableau DATA Saberです。
社内のデータ活用促進文脈で、エンジニアと非エンジニア(ビジネスサイドメンバー)の連携方法を模索しているお話をします。
どこの会社でも「あるある」のデータ活用課題を解消すべく、取り掛かった勉強会のお話です!
こんな場面、身に覚えはありませんか?
非エンジニア(ビジネスサイドメンバー 以下 ビ):「施策を打ったので効果測定のための●●のデータありませんか?」
エンジニア(以下 エ):「あーそれなら、このデータ使ってください(ちくちく抜き出し作業)」
ビ:「ありがとうございます~(あれ、なんか思ってたのと違うデータだし、これでは効果が分からないな。)あのーー、他にXXのデータありませんか?」
エ:「うーん、それを確認するのは工数が結構かかるんだけど、、、」
ビ:「そうなんですね、わかりました。」(シュッと消える)
後日ふと目にした報告書には、、、
「エンジニアに確認したところデータが取得が困難との回答のため、データ詳細は不明」
ーーーーちーんーーーーー
このような『すれ違い』は、多くの職場で見られる課題です。双方に悪気はありませんが、結果的にビジネスのスピードが落ちてしまいます。サービスを提供しているお客様にもいい影響があるわけありません。 「コミュニケーション不足なんじゃない?お互いコミュニケーション取っていこうよ!!」という正論、簡単にはいかないことは皆さんご存じですよね。
そこで、、、
エンジニアも非エンジニアもごちゃまぜの「GA4勉強会」はじめました。
(やるよって言ったら、対象のプロダクトのマーケティング、CSだけじゃなく別プロダクトのエンジニアやPdM、デザイナーもどんどん手を挙げてくれて総勢16名に。ほんとそれが千株式会社の素敵なところ。)
で、結局ツールを理解して、ビジネスサイドも自分でデータ取れるようにするってことが正解なの? と思ったとこのあなた。もちろんそうですが、そこだけを狙っているわけではないのです。
このGA4勉強会は「自走する学習コミュニティ活動」の爆誕を意味しています。 GA4セミナーを受けましょう、ではないのがポイントです。
<勉強会の目指す姿>
「自走する学習コミュニティ」
 学習コミュニティと銘打って、集団学習を奨励していきます。わからないことを気軽に聞けるメンバーがいるという状態を作り、心理的安全性の確保をします。そして、複数人が同じ方向に向かっているので、ナレッジの共有が行われ、ギブ&テイクの流れがでます。そうすれば、誰かの異動や退職で途切れることはありません。
学習コミュニティと銘打って、集団学習を奨励していきます。わからないことを気軽に聞けるメンバーがいるという状態を作り、心理的安全性の確保をします。そして、複数人が同じ方向に向かっているので、ナレッジの共有が行われ、ギブ&テイクの流れがでます。そうすれば、誰かの異動や退職で途切れることはありません。
誰かに教えてもらうのを待つ、わからないから丸投げするのではなく、当事者たちが学び合い解決方法を見つけるのです。この流れがうまく回れば、コミュニティ活動は自走し始めます。主催者のやることはこの流れをスムーズに途切れなく回していくことだと考えています。
主催者としての「学習コミュニティ活動」アシストをまるっと記載
1.職種ごちゃまぜで共通のビジネス課題を整理する時間を作る
2.課題解決のための方法を調べる、学ぶ、わかる人に聞く場を用意する
3.やれることは自分達で、できないことは有識者にお願いし、課題を解決する
4.解決したら他のグループや周りに成功事例として報告する会を開催する
5.今度は誰かの課題を一緒に解決するように次の場を設定する
はい、勉強会題材の専門知識は必要ないです! エンジニアも非エンジニアも一緒にコミュニティ活動をすることが、データ活用課題の解決に直結すると信じて走っていきます!
おわりに
現在、勉強会2回目が済んだところです。
前半はベース知識の共有時間が多く、ほとんどの人が受け身になってしまう状況でした。場がなかなか温まらない中、手を挙げてくれるメンバーがいたり、追加情報を共有してくれたり、徐々にですが複数人の学習効果できている感じがしました。
次回はワークショップ型の課題整理会を開催予定。エンジニアも一緒にグループに分かれて、ビジネス課題を整理し共有していきます。 途中で難しいことも出てくるでしょう。できないことも出てくるでしょう。乗り越えられるように主催者として奮闘していく所存です。
正直この勉強会がどの程度成功するかはまだわからないです。半年後にどんな課題があって、どんな成果があったかなどご報告できればいいなと思っております。
ここまで読んでいただきありがとうございました! そんな千株式会社に興味がある方はこちら sencorp.co.jp